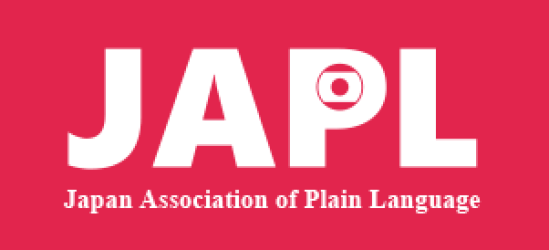軽電子機器協議会にお招きいただき、各社の知的財産部の方々とプレインランゲージについて話した。
学校教育で「特許は独占権」と教えられているが、知的財産部の方々が気づいている通り、特許は知的財産権に関わる交渉を有利に導く道具に過ぎない。独占権という誤解を突いて新規株式上場(IPO)の際に「強力な自社特許」をうたうベンチャー企業があるが、これは投資家に過剰な期待を抱かせる恐れがある。
そんな話をしたうえで、僕はプレインランゲージ国際標準を紹介した。投資家を含め一般読者に対するコミュニケーションは「読者は必要な情報を入手できる」「読者は必要な情報を簡単に見つけられる」「読者は見つけた情報を簡単に理解できる」「読者はその情報を使いやすい」という四原則に沿う必要がある。プレインランゲージ国際標準はこれら四原則の詳細を提示する。
これに対して、「一般読者どころではなく、社内の研究者とコミュニケーションをとる際にも、プレインランゲージが必要だ」という反応が知的財産部の方々から返ってきた。確かにそうだ。「クレーム」は「苦情」ではなく「特許請求の範囲」の意味である。突然、「クレームを見直してほしい」と言ったら、研究者は戸惑うだろう。
科学技術に関する情報を広く国民に向けて提供する科学コミュニケーションでは、情報は倫理的に提示しなければならない。一方的な立場や解釈を立つことなく、データはフェアに、バイアスなく提示する必要がある。例えば、ワクチンについて話すなら、効果と共に副作用についても公正に伝えるのがよい。
主要国首脳会議(G7)科学技術担当大臣会合(仙台、2023年)で、科学コミュニケーションについてワーキンググループ(WG)を設置することになった。ワクチンやAIについて正確な情報が国民に伝わらないという課題にG7各国が懸念し、WGが設置されたのだ。どのようなテーマをどのように伝えるかを検討するのがWGであって、一方、情報提供の手法はISOのプレインランゲージ標準化グループで国際標準化が進んでいる。両者が連動することで、科学コミュニケーションは改善されていく。先に触れた「情報は倫理的に提示する」は現在検討中の国際標準案にある一文である。
広く国民に向けた科学コミュニケーションについても、知的財産部の方々に理解していただいた有意義な会合となった。