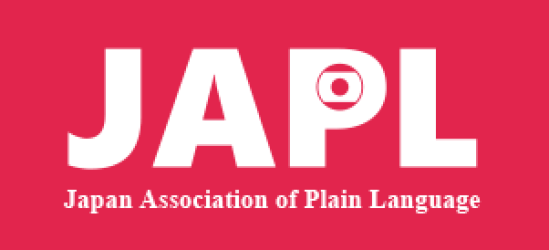1月29日に東京都主催の「アクセシブルツーリズム推進シンポジウム」に登壇した。今年は東京で耳が聞こえない、聞こえにくい人たちのオリンピック(デフリンピック)が開催される。急増するインバウンド旅行客も日本語音声は理解できない。これらの人向けに文字による情報提供を呼び掛けたうえで、「情報発信はコンパクトに」と、プレインランゲージ原則について話した。
観光庁は「観光立国実現に向けた多言語対応の改善・強化のためのガイドライン」を2024年に公表した。文字による情報提供については、次のように推奨されている。
- 名称・標識・サイン・情報系は、提供情報が明らかに訪日外国人旅行者にとって利用価値が低い場合を除き英語併記を行うことを基本とする。
- 施設特性や地域特性の観点から、中国語又は韓国語等の表記の必要性が高い施設については…中国語又は韓国語を含めた表記を行うことが望ましい。
京成スカイライナーの車内表示板は、行き先が日本語、英語、中国語、韓国語で順番に表示する。日本語がわからない旅行客が多いから、まさに施設特性に基づく情報提供である。
都心を走る電車でも、四か国語で次の停車駅を表示している場合がある。しかし、次の駅まで二分の電車で中国語や韓国語表記をしていると、情報の取得に時間がかかりすぎ、降りられなくなる恐れが生じる。

情報発信は、それを受ける人の目的を満たすようにコンパクトに行うのがよい。ユニバーサルスタジオシンガポールには、ボートに乗って流れを進むアトラクションがある。このアトラクションの入り口には、「濡れるよ、びしょ濡れかも」と英語と中国語で書かれている。黄色背景に黒字という目立つ表示で、文字サイズも大きい。その下には、ポンチョ売り場やロッカーの案内が小さく書かれている。コンパクトな情報発信の好事例である。